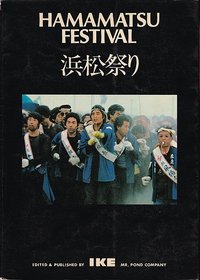› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › ④町内のまつり、町民主催の町内の伝統行事であるということ
› ~凧合戦と屋台~ NAVA@八まん連 › ④町内のまつり、町民主催の町内の伝統行事であるということ2017年07月29日
④町内のまつり、町民主催の町内の伝統行事であるということ

私の考える浜松まつりの四つの構成要素、最後は、町内のまつり、町民主催の町内の伝統行事であるということ、について書きます。
年が明けると町内は5月に向けて動き始めます。看板が取り付けられ、凧の修理などの準備も始まります。
ラッパやお囃子の練習が始まるようになると、お父さんお母さんたちも毎日のように公会堂に集まってきます。
屋台に提灯が掲げられ、お囃子総ざらえの頃には、みんながひとつのチームのように打ち解け合います。
私はこのような町内の雰囲気が好きです。
たびたびの引用になりますが、映画「合戦」の青池監督の言葉を再度紹介します。
-映画 凧合戦を語る会ブログから引用-
【映画『合戦』は何をえがいたか】
これは、見ていただければ瞭然のことですが、若干の蛇足を書きますと、わたしがこの映画で提示したかったことの一つは「コミュニティの力」です。
凧揚げの醍醐味は、合戦場でのあの勇壮さにあることはいうまでもありませんが、わたしが、それとおなじように興味をもって映像にしたのは、コミュニティ(町内)の人たちが5月の3日間へ向かって準備を進めていくプロセスでした。凧を揚げるという目的のために、老若男女が知識や知恵や技術を出し合い、恊働する。
——そこには、上下の人間関係ではなく、みんなが横一線で自分の持てる力を発揮する姿がありました。そんな「コミュニティの力」を、わたしたちの日常生活にも活かせたらといいな、といまでも考えています。
-引用終わり
そして我々はずっとこれを続けてきました。なかには初が一軒も無い年があったかもしれません。それでもやるのです。
それが町の伝統だから。
あっては欲しくないですが、豪雨や震災に突然見舞われるリスクがあります。どこまでの事が出来るか分かりませんが、町内がまるで一つのチームのようにお互いの顔と名前を知っているというのは、尊い事ではないでしょうか。
偽の歴史にいつまでも頼っていたり、綺麗な言葉で飾らなくても、これが「浜松まつりの意義」と胸を張って言っていいと思います。
以上、4回に渡って「浜松まつりにはいくつかの性格がある」というお話をさせていただきました。今回訳があって個人の主観を積極的に出しましたが、今後はもう少し抑えるつもりでいます(くどいので)
Posted by NAVA@八まん連 at 19:35│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。