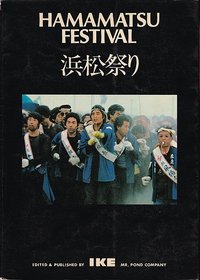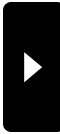2011年12月08日
浜松まつりの歴史③
浜松百撰 1962(昭和37年)より
オッペ組以後 大島義雄(元浜松祭本部理事)
浜松に生れ、浜松で育ち、そうして、やがては浜松で死にたいと思っている僕にとって凧揚げはまさに浜松の真髄、'ますらをぶり’の極致だ。ここには、人間の烈しく純粋なものが煮えたぎっているように思われる。だから、どんなに時代が変わろうと、凧だけは純粋な形で残したいという、やみくもな気持がある。
とくに最近とみにオシロイ臭さをましてきた浜松祭を見るにつけ、そう思うのだが、考えてみれば、僕たちが若かった頃の凧は、荒っぽいといえば確かに荒っぽかった。
いま僕の頭の中で、おぼろにカスみながらも消え失ってしまわない凧の最初の記憶は、オッペ組一党の一種おどろおどろしい印象である。当時、泣く子も黙る「ざんぱの左平」「はんこます」「黒亀」といった名うての暴れん坊に率いられた一党は、米騒動の後の街を、シャレコーベ印の凧をかついで、オッペ、ワッショ、の掛声も物凄く、鉄工場めざして馳けて行った。この掛声は、凧場会場ではむろんのこと、遊郭は雨戸をとざし、道行く人も思わず横道に避けたという。しかし、よし悪しは別として、さしずめこのオッペ組あたりは、凧揚げ中興の祖といったところだった。大正八、九年ころのことだ。
大体、ワッショ、ピッピッというあの相の手に入る呼子、これも初めからああだったのではなく、今からざっと三十年くらい前、ワッショ、ワッショばかりではノドが乾いてたまらないというので、水野正さんあたりが頭をひねった挙句のアイデアで、おかげで掛声に中休みができて後世の連中が大いに助ったというわけである。
凧揚げの本当の達者は、今では数えるほどになってしまったが、僕たちが中堅どころだった昭和五、六年には、天神町のコンニャク屋を筆頭に、糸づけ、凧上げ、凧作りの所謂テング連というのが各町にいて秘術をつくしたものだ。
今時、凧を真っすぐ上げるのは旦那凧、左肩を下げて揚げなければケンカにならないということさえ、果して何人が知っているだろう。一尋九匁五分の大綱で切り合って両々相譲らず、挙句がテギの肉弾戦の往時、凧は本当の"いのち"を持っていたのではなかろうか。
Posted by NAVA@八まん連 at 00:17│Comments(2)
│凧
この記事へのコメント
前回の井泉水居士の文もよかったのですが、いいですね、この文章。
凧場の砂煙と人いきれ、そして合戦の喧騒。
いろいろなものが匂いたち、そして聞こえてくるようです。
凧場の砂煙と人いきれ、そして合戦の喧騒。
いろいろなものが匂いたち、そして聞こえてくるようです。
Posted by 酒上不埒 at 2011年12月08日 23:37
>酒上さん
コメントありがとうございます。
言いたい事や書きたい事が山ほどあるのですが、私が書くと個人の主観や思い入れとの区別が出来なくなってしまうので、まずは論評抜きの事実(その時代のメディアに掲載されていた事実)として投稿しています。
もちろんコメント大歓迎です。
みなさんが感じ取ったことをコメントいただければありがたい。
それにしても、人づてに聞いていた過去のことを、こうした文章でみるとまたすごいですね。昭和初期・・・むぅ、思わずうなってしまいます
コメントありがとうございます。
言いたい事や書きたい事が山ほどあるのですが、私が書くと個人の主観や思い入れとの区別が出来なくなってしまうので、まずは論評抜きの事実(その時代のメディアに掲載されていた事実)として投稿しています。
もちろんコメント大歓迎です。
みなさんが感じ取ったことをコメントいただければありがたい。
それにしても、人づてに聞いていた過去のことを、こうした文章でみるとまたすごいですね。昭和初期・・・むぅ、思わずうなってしまいます
Posted by nava at 2011年12月09日 01:30
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。