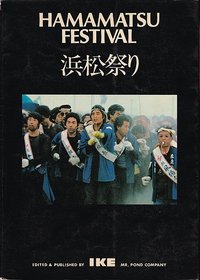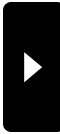2011年12月09日
浜松まつりの歴史⑤
浜松百撰 1962(昭和37年)より
『凧合戦』 鷹野つぎ
端午の節句の日に浜松名物の凧合戦がありました。
用いられる凧は、美濃紙八帖ばりとか十帖ばりとか申していたものでした。その尾には飾繩の太いものが使われ、その長い尾にはウナリがつけられました。
学区には、それそれ消防ポンプなどを納めておく倉庫風の建物がありましたが、私の下垂町でも凧まつりの当日が近づきますと、新装の大凧がそうした建物の天井から取り出されてきました。そして辻の広場などで係の青年たちは糸目をたしかめたり、尾の工合をしらべたりして準備をととのえました。
いよいよこの日がきますと、町名を代表した大凧の行列がありました。たとえば学区の頭字を平仮名であらわしたものや、なにがしの町ならば天狗とか、どこそこは登竜とかいうように、それぞれきまっていました。それらの凧が三十四ほどの学区の数だけありますから、行列の賑わいもなかなかたいしたものでありました。
ワッショイ、ワッショイという掛声と一緒に、大凧の列はそれぞれの学区の青年たちに、その縁をぐるりと囲まれ、頭上に捧げられながら街を練って行きます。青年たちは身軽なメリヤスの下着などで、襟に所属の色とりどりの手拭を結んでいました。 子供達は子供達で二畳敷くらいの凧を頭上に捧げて、大人連を小振りにした格好で、同じく町はずれの野原の方へと従いて行くのでした。
野の広場では字区々々で思い思いに陣をとり、それぞれの用具を配置し、指揮者の釆配によって、合戦の準備がととのえられるのでした。まず追風に向って凧が捧げられるとともに、地上にしっかり杭でとめられた糸ワクから揚糸を繰り出す準備がされます。やがて気を量って放たれた凧は、長い尾をスルスルと地上からはなし、風に乗ってぐんぐん上昇して行き、額ぶちくらいの大きさに見える高さになって空中におちつきます。しかしウナリは耳近く風をきって、グーン、グーンと勇ましく響きます。
すべての字々の凧がそうして揚りますと、いよいよ合戦が始まるのでした。私も、姉やお友達とつれだって、あぶなくない場所で見ているのでした。というのは凧を揚げる陣地のありさまは、見ていても一生懸命でこわいようでしたから。
まず合戦の発端を云いますと、静かに揚っている一つの凧の糸目の下へ、他の一つが潜ってはいって行きます。とたんに潜られた凧は非常な勢いで糸を詰めたりゆるめたりします。潜った方ではどんどん糸を引き寄せ、また術を凝らして先方の糸の緩急に呼吸を合せます。結局こうして双方の糸にはげしい摩擦が起りますと、どちらかの糸がプツリと断ちきられるのでした。時には二つの糸がからみ合って、一緒にプツリと切れてしまうような珍しい勝負もありました。
こういう空の眺めを作りますまでには、陣地の働きも真剣なものでした。
そこには陣地全体の呼吸の一致がありました。采配を振る一人の指揮者に従って、糸をゆるめる時、糸を引く時、多数の青年たちは全く一つの動作の、一つの手であり、足であるように働くのでした。糸がゆるめられる時は、糸ワク車の糸がガラガラとウナリを立てて繰り出されました。引くときにはこぞって各自が手にもった筬型の糸挾にぴいんと鉄棒のように張りきった揚糸をかけて、自分たちの凧には背を向けつつ必死となって引きます。指揮者の号令のある限りは、タッタ、タッタと足音の絶え間もなく引くのでした。
私たちは誰れも自分の住む字の凧を見上げていました。「ああ困るわ、負けては困るわ」と、姉たちも胸をたたいて気をもんで下垂町の「し組」の凧を見ているのでした しかし、プツリと切られて尾をまいてくるりくるりと落ちて行く凧を見るときほど、それがどの字の凧であってもあわれを思わせるものはありませんでした。
※鷹野つぎ「四季と子供」より~ 筆者は浜松出身の作家、浜松の四季をテーマに子供を描いた「四季と子供」は有名。これは昭和16年の古今書院版から復刻した。ちなみに下垂町はいまの池町辺である。
Posted by NAVA@八まん連 at 23:02│Comments(0)
│凧
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。