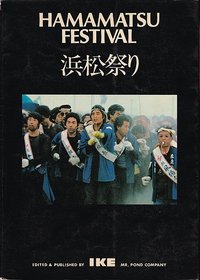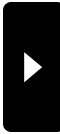2009年12月09日
豊田佐吉作 明治時代の浜松凧発見

昨日の中日新聞にトヨタ創始者の豊田佐吉が作った浜松凧が見つかったという記事が載っていた。豊田佐吉の出身地は湖西市であり、今は豊田佐吉記念館として保存・公開されている。会社の関係で何度か佐吉記念館には行ったことがあり、湖西のほうで揚げられるごぼち凧が飾られているのも知っていたが、豊田佐吉が浜松凧までも研究し、作っていたとは意外だった。
写真を見て分かるとおり、現在の浜松凧とほぼ同じ、正方形で骨の本数が多いタイプである。明治22年作というからまだ東海道線が開通するかしないかの頃、浜松への移動もひと苦労の時代での佐吉の研究熱心さもさる事ながら、浜松の凧が湖西にまで知れ渡り、明治22年にすでに現在と変わらない浜松凧のスタイルが確立されていたのも驚きだ。
遠州地方は古くから各地に初凧の風習があり、湖西地区でもごぼち凧というのを揚げているが、こちらは骨の本数が数本程度。この写真でも骨が22本もあり、浜松凧は一線を画している。
骨が多い=あえて重い=重力で落下する=糸が素早く出て行く かつ頑丈
揚げるだけだったら骨は極力少ないほうがいいに決まっている(近年見かける大枡凧しかり)。浜松凧も当初は揚げるのに最低限だった骨の本数が、必要に応じて増えていったと推定する。それが明治の22年に確立されていたのではないか。
他地区とは一線を画すこれら浜松凧の示す意義と伝統とは何かを考えたい。
Posted by NAVA@八まん連 at 21:52│Comments(0)
│凧
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。