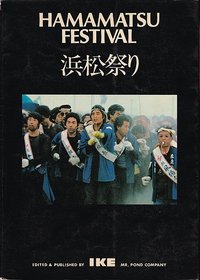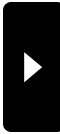2012年07月31日
浜松八幡宮の歴史 延喜式
昨日に引き続き浜松八幡宮に関する記事です。
境内に入ると、このご由緒書が目に入ります。
ブログ管理者の個人見解ですが、少し噛み砕いてみようと思います。

昨日の記事のつづき
~そして許部神社は「延喜式」の敷智郡六座の神の中に登録され、極めて由緒ある神社とあります。~
延喜式とは
延喜式(えんぎしき)とは、平安時代中期(927年)に編纂された格式(律令の施行細則)で、三代格式の一つである。国のまつりごとの運営マニュアルと考えればよいのではないでしょうか。
式内社
この延喜式の9巻・10巻は延喜式神名帳(神社の一覧表)と呼ばれていて、当時の官社(国家が祭祀した神社)3132座(2861所)が記載されている。延喜式神名帳に記載のある神社を一般に式内社と言い、記載のない社は式外社と呼んで式内社は社格の一つとされ、当時朝廷から重要視された神社であることを示している。
敷智郡とは律令時代の遠江国の郡(こおり)の名前。そして六座とは舞阪の岐佐神社、雄踏の息神社、参野町の津毛里神社、呉松の曾許乃御立神社、神ヶ谷の賀久留神社、そして許部神社(八幡宮)の6座を指します。
Posted by NAVA@八まん連 at 00:52│Comments(0)
│歴史
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。