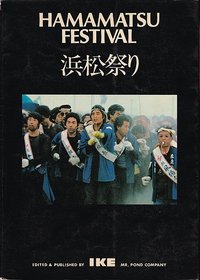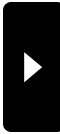2012年08月07日
中世浜松の都市 引間宿 (引馬宿)について考える
江戸時代の主要街道は東海道であり、浜松城の大手門付近から南に宿場町が形成されました。
では、江戸時代以前はどうだったのでしょうか?
江戸時代以前の浜松は斯波氏や今川氏による争いが長く続いていました。
その頃の遠州の中心地は、現在の浜松城ではなく、東海道が馬込川にさしかかるあたりに引間(ひくま)という市場町があり、その引間を見下ろす三方原台地上に築城された引馬城が、遠州の中心地として君臨していました。
中世の都市「ひくま」はその正確な位置は分からない「謎の都市」といわれていますが、浜松市博物館の資料を見ると八幡町~早馬町付近に宿があったとする研究が進んでいるようです。
引用元:浜松市博物館報14 『特集:浜松の中世を考える』(2001,浜松市博物館)より。
「ひくま」は現浜松市街地に想定されるが、実は正確な場所も判明していない。
馬込川はかつて小天竜と呼ばれ、さらに時代をさかのぼれば、天竜川本流のひとつである。
馬込川西岸の船越町は、江戸時代、馬込川の水量減少によって渡船が衰退すると、既得権を主張し、集落から遠方とはなるものの、大天竜 (現天竜川) において渡船業務を継続した記録が残る。
中世後期の街道が船越町付近で天竜川の一流を渡ると考えれば、この付近から浜松八幡宮のある八幡町、早馬町付近にかけて「ひくま」宿を想定するのが自然である。
これを裏付けるものとして、静岡文化芸術大学建設時の試掘調査では遺跡の一部も発掘されたようです。(現文芸大=元東小学校=元専売公社)
浜松荘域では、野口町の静岡文化芸術大学建設に先立って試掘調査を実施した。東小学校校庭遺跡として登録されていた場所にあたる。灰釉陶器や山茶碗の破片のほか、内耳鍋片などが採集されている。
度重なる建設工事によって撹乱を受けており、河川砂も検出されたことから、もともと河川敷に近い場所で、遺跡本体はこの場所ではなく、近接地にあると考えられた。
この地の小字「黒地蔵」は、北西にあたる八幡町側を中心とした地名と考えられる。
平安後期から中世を通じて栄えた引馬宿は、同町八幡宮から早馬町にかけての、馬込町 (かつての天竜川主流域のひとつ )自然堤防上を中心とし、また船越町が当時の天竜川の渡しとして推定されてはいるが、実体はいまだはっきりしない。
「早馬」は江戸時代の伝馬制よりも古い制度であり、この地名は示唆的である。
船越町は、江戸時代においても池田とともに天竜川の渡船を請け負った。小天竜と呼ばれた馬込川の渡しが、流量の減少によって廃止されても、集落から遠方とはなるものの既得権を主張し、大天竜 (現天竜川) において渡船業務を継続した文書が残る。
出土品は、引馬宿の時代を反映しており、想定地北西付近に中世を通じた遺跡が埋まっている可能性が高まった。
元城町の東照宮境内から出土したかわらけは一括性の高い資料で、古城という伝承通り、徳川家康入城以前の引馬城が今川支配下で機能していた時期を示す。
古城は早馬町から船越町付近を見下ろす河岸段丘上にあり、引馬宿の支配層の居館としてもふさわしい (「浜松城跡」ほかに既掲載 )

浜松八幡宮の御由緒書に残る、八幡太郎義家(源義家)の当地での参篭は、わざわざ義家がこの付近まで来たのではなく、主要街道及び宿が八幡宮付近にあったからだと考えればすっきりします。
さて、もうすぐ八幡宮の例大祭(8/14・8/15)ですね。
このブログで興味をもたれた方は是非境内の御由緒書を見てください。
次回以降はもう少し引馬宿について掘り下げてみようと思います。(第一部、完)
Posted by NAVA@八まん連 at 22:16│Comments(2)
│歴史
この記事へのコメント
小字の「黒地蔵」という地名に興味を持ちました。
これは万福寺の黒衣地蔵と関連づけて考えることもできましょうし、あるいは遠州弁の「クロッチョ(隅)」に通ずる「馬込川の畔(くろ)に建立された地蔵」の文字転訛として考えることもできるかもしれません。とすれば、渡河集落としてのこのエリアの歴史をもっと考えてみたいですね。
大井川の例を引くまでもなく、古来、渡河・渡津は集落や都市の形成にとって重要な要素を果たしています。古天竜としての馬込川に渡河集落の形成がされていたであろうことを考えると、馬込河畔の歴史にさらなる注目が必要ですね。
これは万福寺の黒衣地蔵と関連づけて考えることもできましょうし、あるいは遠州弁の「クロッチョ(隅)」に通ずる「馬込川の畔(くろ)に建立された地蔵」の文字転訛として考えることもできるかもしれません。とすれば、渡河集落としてのこのエリアの歴史をもっと考えてみたいですね。
大井川の例を引くまでもなく、古来、渡河・渡津は集落や都市の形成にとって重要な要素を果たしています。古天竜としての馬込川に渡河集落の形成がされていたであろうことを考えると、馬込河畔の歴史にさらなる注目が必要ですね。
Posted by 酒上不埒 at 2012年08月08日 23:09
僕が子供の頃、黒衣地蔵は万福寺よりも更に東にお堂がありました。
常盤町との境を(六間からみると)斜めに走る道沿いの、野口町との境でした。区画整理に伴って万福寺に移されたと記憶しています。
今となってはこの"斜めに走る道"が明治以前の道筋であり貴重なものだと思いますが、あと何箇所か、当時の地図と符号する道筋があります。追って言及します。
第二部は、ご指摘のとおり川にまつわる話しからスタート予定です
常盤町との境を(六間からみると)斜めに走る道沿いの、野口町との境でした。区画整理に伴って万福寺に移されたと記憶しています。
今となってはこの"斜めに走る道"が明治以前の道筋であり貴重なものだと思いますが、あと何箇所か、当時の地図と符号する道筋があります。追って言及します。
第二部は、ご指摘のとおり川にまつわる話しからスタート予定です
Posted by nava at 2012年08月09日 01:41
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。