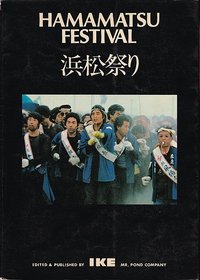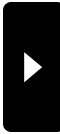2012年08月05日
八幡太郎義家

ふたたび浜松八幡宮のご由緒書きに話しは戻ります。
浜松八幡宮は昔から武家の信仰を集めたとされ、次のような記述があります。
「武家の信仰」
1051年、後冷泉天皇、永承六年、八幡太郎義家が、陸奥に出陣の際、当社に参篭し、源氏の氏神である八幡社を喜び、武運を祈って
契あれば帰り来るまで石清水、かけてぞいはふ浜松の里
と詠進し、武運を祈って社前の楠の下に旗を立てたと伝えられ、「御旗楠」とよんでおりました。これが、現存する「雲立の楠」の起源とされています。
この八幡太郎義家とは、源義家のことですね。
どんな人だったか、触れてみたいと思います。
源義家(みなもとのよしいえ) 1039年-1106年
清和源氏に発する河内源氏の嫡流として、7歳の時、岩清水八幡宮で元服、 よって八幡太郎と号す。
全ての源氏の中で「八幡太郎」義家の血脈は燦然と輝く。
後に武家政権鎌倉幕府を開いた源頼朝、室町幕府の足利尊氏などの祖先に当たる。
・武将の神様。
・天下第一の武勇の士
・驍勇絶倫にして、騎射すること神の如し
と称される。
徳川家康の"家"の字は、源義家からとったともいわれる。
こちらのHPから以下引用。浜松八幡宮の記事もあります。
源頼義の長男で、八幡太郎と称します。
前九年の役で父に従い、その功績により康平6年(1063年)出羽守に任じられました。
永保3年(1083年)陸奥守・鎮守府将軍。
後三年の役に介入し、清原(藤原)清衡を援助して鎮圧しました。
朝廷はこれを私闘として行賞を認めなかったため、私財を将士に提供しました。
このことで武家の棟梁としての名声が逆に高まり、東国武士団との主従結合は強化されました。
承徳2年(1098年)正四位下に叙され、院昇殿を許されましたが、晩年は嫡子義親が追討されるなど、朝廷内で苦しい立場におかれました。
Posted by NAVA@八まん連 at 15:28│Comments(0)
│歴史
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。