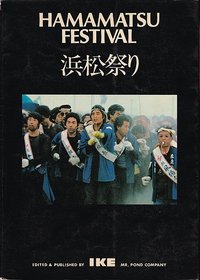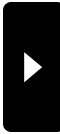2012年08月03日
日本史のテストに出るかも
今日の話題は、歴史の教科書に出てくるお話しです(たぶん高校の日本史くらい)
「遠江國風土記伝」の著者、内山真龍は有名な賀茂真淵に入門していました。
また、賀茂真淵は「曳馬拾遺」の著者、杉浦国頭に学んだともされています。
それではその賀茂真淵とはどんな人なのか、おさらいしておきたいと思います。
賀茂真淵とは国学四大人の一人。
1697(元禄10)年3月4日、遠江国敷智郡浜松庄伊場村(現:浜松市中区東伊場一丁目)で賀茂神社の神官をつとめる岡部政信の子として生まれた。1707(宝永4)年、真淵が11歳の頃、諏訪神社の大祝杉浦国頭(すぎうらくにあきら)の妻である雅子(真崎)に手習いを教わるようになった。そして真崎の夫国頭にも和歌・古典を学ぶようになり、国頭が主催する和歌会などにも参加している。1723(享保8)年、27歳のとき、岡部政長(父政信の甥)の娘と結婚。しかし、翌年9月4日には最愛の妻が病死してしまう。その悲しみは『岡部日記』にも記されている。
1725(享保10)年29歳のとき、父政信のすすめにより浜松本陣の梅谷家に婿入りし、2年後には真滋(ましげ)が生まれている。父が他界すると、1733(享保18)年、37歳のときに伏見(現:京都)へ上って荷田春満(かだのあずままろ)について学問を学んだ。延享三年(1746)50歳の時に御三卿の田安宗武(八代将軍吉宗の次男)に和学御用として仕えたのちは、宝暦十年(1760)研究に没頭し隠居した。門人も本居宣長はじめ優秀な門人を多数養成した。享年73歳江戸で亡くなる。
1818(文政元)年、真淵の50年遠忌が浜松宿梅谷本陣において開催された。
杉浦国頭とは浜松諏訪社の神官で遠江国学の祖といわれる。
武士階級に受け入れられた儒学に対して、国学は神職や庄屋、名主、年寄、地主や町人の代表者などに普及した。 生涯1678(延宝6)年8月23日医師渡辺家の次男として、現在の千歳町に誕生。諏訪社の杉浦家を継いだ。
杉浦国頭は1701(元禄14)年24歳のとき江戸滞在中に和歌を学び、荷田春満(かだのあずままろ)にも面会して和歌の指導を受けた。国頭は春満に将来を期待され、春満の姪である真崎を妻に迎えている。真崎は内助の功があったばかりでなく、春満の学問を浜松に伝えた重要な女性ともいえる。11歳の賀茂真淵が真崎の手習いを受けている。 1705年国頭ははじめて自宅で歌会を開き、荷田春満も何度か浜松の杉浦家にきて和歌を指導した。浜松に若を詠む者が次第に増加すると、国頭は1720(享保5)年11月から毎月一回月並歌会を開催。1753(宝暦3)年まで多少の中断はあれども、ほぼ34年間続けれられた。国頭は歌会を開いて歌道を広めるほか、浜松の有志に百人一首や日本書紀の講義をして古学の振興に尽力した。 1740(元文5)年6月4日63歳で死去。妻の真崎は1754(宝歴4)年2月29日死去。広沢西来院に墓がある。
色の付いた部分は、今後のキーの部分です。
HP『浜松情報Book』http://www.hamamatsu-books.jp/index.htmlより、引用
参考
『浜松市史』
『浜松の史跡』(浜松史跡調査顕彰会)
『浜松歴史散歩』(静岡新聞社)
『はままつ歴史発見』(静岡新聞社)
『賀茂真淵の話』(賀茂真淵翁遺徳顕彰会)
Posted by NAVA@八まん連 at 00:47│Comments(0)
│歴史
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。